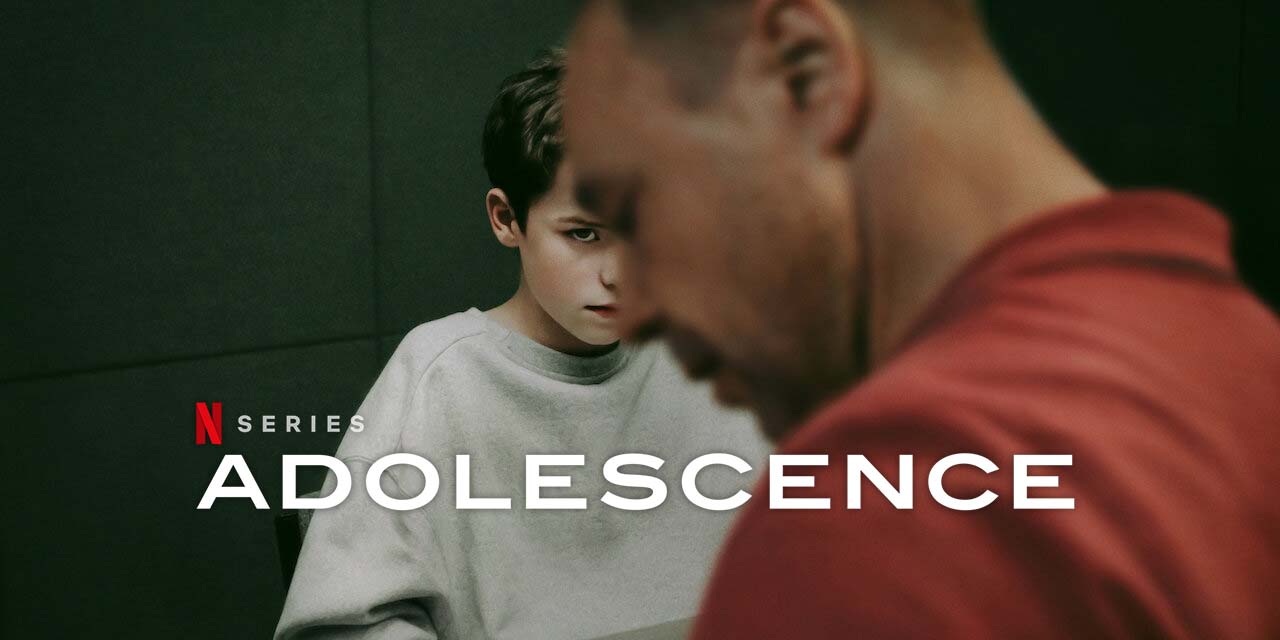
正直なところ、このテーマに言及するのはあまり気が進まない。公的に解決を図るのが難しい問題は語りづらい。経済や世代間の格差はまだ辛うじて客観的に分析しうる。分析可能ということは全体の傾向に則って政策を反映させやすく、有力な効果も期待しやすい。
すなわち、お金がない人にお金を配る、雇用がなかった世代のために雇用を創出する。もちろん一言で言えるほど簡単ではないが、どうすれば解決に近づくのか分かっているだけでも話は早い。対して、男女の営みに対する不満はそうはいかない。富や雇用機会は分配できても恋人は分配できないからだ。そういった悩みは当人にしか解決できない。その手の問題を無理に扱った時、大抵は悲劇が起きる。
作品概要
本作「アドレセンス」は一話全体をワンカットで撮影したたいへんな意欲作だ。冒頭、完全武装の特殊部隊が民家に突入するシーンから物語は始まる。間もなくその家に住むごく普通の父親、母親、姉が銃口の前に制圧されると、次いで上階にいる容疑者――十三歳の少年――が取り押さえられる。恐怖に身がすくんで粗相までしたひ弱な少年に、なんと殺人容疑がかけられていると言うのだ。

典型的なサスペンスであれば無実の子どもが巨大な陰謀に巻き込まれた話だと思うだろう。だが、序盤でカメラの中心を務める刑事の表情は確信に満ちており、そこに悪意の気配はみじんも感じられない。ただ形容しがたい緊張感だけが漂っている。続いて、勾留の手続きが粛々と進められていく。
未成年の容疑者に付けられる「適切な大人」という公的な保護者や、勾留中の権利を説明する警察官、身体の具合を丁寧に尋ねる看護師、刑事と相対して逮捕の正当性を確認する弁護士など、少年の人権を保護するためにあらゆる大人たちが責務をまっとうする様が描かれる。
この辺りで、陰謀の線はほぼ消えたと見える。わざわざ長回しで勾留の手続きを映し出すのには明確な意図がある。これらのシーンは容疑者の少年に特別に親切なのでもなく、かといって特別な策略が隠されているのでもなく、通常の業務の一環に過ぎないことを強調している。
一方、両親としては息子が身に覚えのない容疑で逮捕されてとても落ち着いていられない。警察署で抗議の声をあげ、息子が「適切な大人」に公的の保護者ではなく父親を指定したと聞き、さっそく甲斐甲斐しく息子に駆け寄る姿、その父親に泣きながら無実を訴える少年の姿は、まさしく固い結束に結ばれた模範的な家族そのものだ。

ところが尋問に移ると事態は急変する。親の知らない間に真夜中に外出していた少年、いつの間にか失くしている上着、そして一話の最後に刑事が決定的な証拠を突きつけた。監視カメラの映像だ。そこには同級生の少女をナイフで滅多刺しにする少年の姿がこの上なくはっきりと映っていたのだった。一体、少年はなぜ彼女を殺したのだろうか?
荒んだコミュニケーション
一話時点で少年が殺人犯なのは確定したので、おのずと残りの話は動機や周辺の人物にフォーカスが当てられる。二話目では中学校が主な舞台に移り、一見して上等な制服と立派な建物に彩られた校舎がその実、受動的な映像授業と素通りの教育指導に堕している実情が明らかとなる。

当然、教師たちは生徒の人間関係をろくに把握していない。現代の子どもたちのコミュニケーションはもっぱらSNS上で行われており、学校内でうかがえる様子からは表面的な関係しか分からない。じきに当初は交友関係なしとされていた少年と被害者少女の間に諍いの痕跡が浮かび上がってくる。
生徒たちがInstagramで送り合っていた絵文字には隠された意味があったのだ。曰く、紫のハートマークは性的な関心、黄色は交友への興味を示している。同様に、赤い薬(レッドピル)の絵文字は「真実への覚醒」、青い薬(ブルーピル)は「虚構の受け入れ」を暗示する。
刑事は「それはマトリックスの話では?」と突っ込むも、意味を説明してくれた彼の息子は「なにそれ?」と訝しむ。なにげに僕にとってはある意味でもっともショックを受けたシーンかもしれない。今時の中学生の子にはもうマトリックスの話は通じないらしい。ともあれ、一連のミームは殺人犯の少年が特定の政治思想に侵されている側面を示唆していた。
「覚醒」とは現代社会において男性が女性よりも不利を背負わされているという”真実”への共鳴、ひいてはその隷従から立ち上がり、自分になびかない女性に報復する野望を表している。これは近年なにかと取り沙汰される「インセル思想」の中核的な考え方である。
ただし、インセルは政治思想であっても必ずしも高らかに名乗りを上げる主義主張とはかぎらない。元はと言えばinvoluntary celibate(不本意の禁欲主義者)の略称に留まり、女性と交際したくてもモテないがために禁欲を余儀なくされている立場を自虐的に表す言葉だった。少年は周りから魅力に劣る印象を持たれていたがゆえに、インセルを暗示する絵文字を送りつけられていた。
最初に送ったのは被害者の少女だ。端的に言うならいじめに近い。同じく複数の生徒が誰かに不適切なあだ名を付けられ、逆に付けられた側も付け返すといった荒んだコミュニケーション様式が定着していた事実も判明する。少年自身も「あいつは馬鹿だからあだ名が『馬鹿』で当然だ」と答えているものの、しかし自分がインセル呼ばわりされる屈辱には耐えられなかったようだ。
インセル思想の侵食

三話目では少年と法廷心理学者とのカウンセリングを通じて、彼がいかにインセル思想に侵されているのかが垣間見える。少年にとってこの法廷心理学者は非常に手強い。自立した美しい大人の女性で、名誉と責任に満ちた職に就き、フレンドリーでありながら抜け目のない質問を繰り出す巧みな知性には、敵意と恋慕の両方を抱かざるをえない。
後者の感情がわずかに上回った時、気が緩んだ彼はその思想の端緒を自ら開陳せしめる。少年が被害者の少女にインセル呼ばわりされたのも、流出した画像をもとに「貧乳」とあだ名されて気に病んでいた少女に対して、彼が交際を試みて拒絶された過去に起因しているのだと言う。
少年はこの一件を「落ち込んでいる女はオトしやすい」とされる合理的な戦略に基づいた、と説明する。むろん、そんなのは短慮な振る舞いにほかならない――結果、気安く扱われて憤った少女は彼をInstagramでしたたかにやり込めた――オトせると思い込んでいた相手に蔑ろにされて傷ついた少年は、刃でもってプライドの回復を図った。これが今回の殺人事件の顛末ということになる。
法廷心理学者との面会でもあどけない少年の顔と、凶悪なインセルの顔が交互に表れる。一話丸ごとを使って描かれる二人の対話、前触れなく沸き起こる激昂と恫喝、心情の吐露……彼にとって女性とは、支配して自分のものにしたい戦利品であると同時に、庇護と愛情を期待する存在でもあるのだ。

やがて話をすべて聞き終えた彼女が別れを告げると、少年はあからさまにうろたえて「僕のこと好き?」と執拗に迫る。中立の立場を守らなければならない彼女は原則論を保つも、それがさらに怒りを加速させる。叶わぬ愛情の代償として破壊を求め、支配欲と庇護欲の狭間で揺れ動く。古代より連綿と続く愛憎が過激思想と結びつき、SNSを媒介にしてかくも青少年の心を毒したのである。
教訓なき教訓
最終話では取り残された家族のその後が描かれる。殺人犯の家族に向けられる世間の目は大方想像がつく。自家用車には落書きされ、近所では公然と噂される。味方をしてくれるのは陰謀論者ばかり。引っ越したところでこのご時世ではすぐに噂が広まる。なんとか気丈に振る舞おうとしていた父親も耐えきれずに周囲に当たり散らしてしまう。

本作の表のテーマがインセル思想への警鐘なら、裏のテーマは原因のない犯罪の提示と考えられる。通常、あらゆる作品には視聴者を納得させる劇的な真相が用意されているのだが、本作にはそれがほとんどない。両親ともに健在で経済的な問題は見られず、父親はやや短気でも大したほどではなく、姉との関係も良好、個室もゲーミングPCも自由時間も与えられていて物質的にも満たされている。
少年を侵したインセル思想とて具体的にどんなコンテンツを見ていて、いつからどれくらい影響を受けていたのかまったく言及されていない。そもそも「インセル思想に侵されて殺人を犯した」との見立て自体、本人の発言や行為から類推した話に過ぎないのだ。恋愛でこっぴどく失敗して相手を激しく憎む青少年など、今も昔も大勢いる。
だが、どうであれ本作の少年は「若さゆえの過ち」では済まなかった。気が強い意地悪な子相手に下手を打って馬鹿にされるなんてそう珍しい話ではないのに、一足も二足も飛び越えていきなり凶行に及んでしまった。結局のところ、この事件について誰もが納得する動機を見出すのは不可能なのだろう。あるいは、本人でさえも。最終話でようやく殺人を認めた彼の胸中はいかばかりか。
翻って冒頭に戻ると、恋愛の貧困は公的には補いがたい問題である。単に交際を望むのであれば、相手に気に入られるようなアプローチを心がけたり、自分を受け入れてもらいやすいように自己研鑽に励むやり方が適切と思われるが、インセル思想は支配欲や被害者意識――傷つけられた男性性を回復するための戦利品として女性を求めるという発想――から出発しているので、どうあがいても現代社会とは共存できない。
しかしながら昨今のSNSで男女論は絶大な人気を誇っている。各々が個人の痛ましい体験に依拠しているゆえ完全な誤りとも言い切れず、むしろ個別的には同情に値する事例も割に多く見受けられる。さりとて、せいぜい恨み節は恨み節程度に留めておいて、普遍的な秩序や社会正義に取って代わろうとする過激思想は控える賢明さをどうか選んでもらいたい。その道に進んでも決して幸福にはなれない。
この種の事件に対して大人たちがとれる対策は皆無に等しい。子どもから今さらインターネットを取り上げても問題は解決しない。それこそ今度は流行の話題についていけなかったり、同世代とのコミュニケーションを事実上断たれたことで違う問題を抱え込みかねない。かといって四六時中、子どもたちを見張っているわけにもいかない。
どの出来事にも必ず辻褄の合う理由が存在するとはかぎらない。兎にも角にも起こる時は起こり、ひとたび起こってしまえば取り返しはつかない。たとえ被害者の少女が少年をインセル呼ばわりしていなくても、話を聞けば他の生徒がそうしたかもしれないし、さもなければ別のきっかけでどのみち同じ相手を殺していたかもしれない。
本作から得られる教訓はない。強いて言うなら教訓が得られないことそれ自体が教訓と言える。どんな話からも教訓を得られると思い込むのは一種の驕りであり、時には腑に落ちない居心地の悪さと向き合わなければならない。あくまで各自の責務に応じて事態の収拾に努めるのみだ。一話丸ごとのワンカット撮影を淡々とやってのけた演出的背景には、そういうリアリズムに根ざしたニュアンスが込められているのではないかと僕は思う。